【岐阜・飛騨高山】春と秋に開催!豪華絢爛な屋台に心踊る、高山祭の見どころを紹介
16-1024x769.jpg)
岐阜県高山市で毎年4月14日・15日と10月9日・10日に行われる高山祭(たかやままつり)は、国の重要無形民俗文化財に指定され、ユネスコ無形文化遺産にも登録された、日本を代表する由緒ある祭礼です。
京都の祇園祭、埼玉の秩父夜祭と並ぶ日本三大美祭のひとつに数えられ、荘厳な屋台(山車)が“動く芸術品”さながらに人々を魅了します。日本屈指の山車祭として知られる春と秋の高山祭、それぞれの見どころをご紹介します。
1.旧高山城下町を南北に二分して、春と秋に行われる高山祭
22.jpg)
16世紀後半から17世紀が発祥といわれる高山祭。伝統的な町並みが残る旧高山城下町を舞台にした山王祭(さんのうまつり)と八幡祭(はちまんまつり)、ふたつの祭の総称です。
4月14日・15日に開催される春の高山祭(山王祭)は、旧高山城下町南半分の氏神様である日枝神社(ひえじんじゃ)の例祭。一方、10月9日・10日に開催される秋の高山祭(八幡祭)は、北半分の氏神様である櫻山八幡宮(さくらやまはちまんぐう)の例祭です。
春・秋ともに、祭の主役は「屋台」と呼ばれる大きな山車。それぞれに趣向を凝らした山王祭12台と八幡祭11台の合計23台の屋台は、江戸時代後期に発達した祭屋台の典型として、1960年(昭和35年)に国の重要有形民俗文化財に指定されています。
さらに高山祭の屋台行事は、1979年(昭和54年)に国の重要無形民俗文化財に指定。2016年(平成28年)には全国32件の祭りとともに「山・鉾・屋台行事」としてユネスコ無形文化遺産にも登録され、世界の財産であると認められることになりました。
12.jpg)
高山祭の屋台の始まりは、1708年(宝永5年)の八幡祭の神楽台。それから40数年後に、山王祭の屋台が現れたといわれています。江戸型の山車が現在のように華やかな屋台へと進化したのは、地域のコミュニティ組織であった「屋台組」の「自分たちの屋台は宝」という強い思いがあったからこそ。火災や破損のたび改修を重ね、他の屋台組に負けまいと、意匠や装飾を凝らしていったのです。
そうして、財力ある豪商・旦那衆に支えられた飛騨の匠たちの見事な技により、精巧な彫刻や漆塗り、飾り細工で彩られた美しい屋台が完成。その姿は「動く陽明門」とも称されています。
25.jpg)
そんな匠の技を伝える伝統の屋台を間近で見ることができる高山祭。春と秋でそれぞれ異なる魅力と見どころについて、紹介していきましょう。
2.風雅な桜に彩られる、春の高山祭(山王祭)
5.jpg)
まずは、高山に春の訪れを告げる「山王祭」。4月14日・15日は桜の開花時期と重なることもあり、大勢の観光客でにぎわいを見せます。華麗な屋台が朱塗りの中橋を渡る姿は、思わず息を呑むほどの美しさです。
●屋台曳き揃え(やたいひきそろえ)
18.jpg)
日枝神社の例祭である山王祭では、12もの豪華絢爛な屋台が安川通りの南側・上町に登場します。神楽台など4台は、中橋のたもとにある御旅所(おたびしょ)にて披露。
それ以外の屋台は14日には神明町通り、15日には上一之町~上二之町とさんまち通りにそれぞれ曳き揃えられます。屋台の美しい意匠を間近で鑑賞できる、またとない機会です。
●からくり奉納
14.jpg)
からくり奉納とは、屋台の上のからくり人形が熟練の綱方に操られ、繊細で巧妙な舞や芸を披露する伝統の奉納行事です。
春の高山祭では12台の屋台のうち、三番叟(さんばそう)、石橋台(しゃっきょうたい)、龍神台(りゅうじんたい)の3台が、御旅所前の広場で順番にからくり奉納を行います。
まずは三番叟が戯曲「うらしま」の音色に合わせて人形を操ります。童子の顔が一瞬で翁の顔になる早変わりの技に、観衆からは大きなどよめきが。続く石橋台では、舞を踊る美女の打掛がめくれると、荒ぶる獅子へと変身。迫力ある場面に目を奪われます。最後は龍神台。唐子が抱える壺から龍神が飛び出し、荒々しい舞を披露すると、陣屋前は拍手喝采に包まれます。
●御巡幸(ごじゅんこう)


神輿を中心に、獅子舞や闘鶏楽(とうけいらく)、裃(かみしも)姿の警固など、数百名にも及ぶ祭行列「御巡幸」は、まるで絵巻物のような華やかさ。日枝神社を出発し、祭礼区域をゆっくり練り歩きます。
氏子の家々の前には、屋台組ごとに意匠の異なる提灯と和傘が飾られ、風情たっぷり。日が暮れると提灯にろうそくが灯り、幻想的な雰囲気が漂います。

●夜祭(よまつり)
28.jpg)
14日夜に行われる夜祭では、昼間とはまた異なる幻想的な世界が広がります。無数の提灯に照らされた屋台が町を巡り、夜桜との雅な共演も。やがて順道場を過ぎると、伝統の曳き別れ歌「高い山」が響き、屋台はそれぞれの屋台蔵へと帰っていきます。
30.jpg)
●春の高山祭(山王祭)各行事とスケジュール(例年)

※雨天時は、屋台曳き揃えとからくり奉納はそれぞれの屋台蔵でお披露目、夜祭は中止
会場:日枝神社周辺
期間:4月14日~15日
TEL:0577-35-3156(高山市教育委員会文化財課内 高山屋台保存会事務局)
3.祭の躍動を体感。屋台曳き廻しも行われる、秋の高山祭(八幡祭)
秋の飛騨高山を彩る八幡祭は、旧高山城下町北半分の氏神様、櫻山八幡宮を舞台に執り行われます。中でも11台の屋台が町を練り歩く「屋台曳き廻し」は、春にはない秋だけの特別行事。歴史絵巻さながらの「御神幸(ごしんこう)」に、幻想的な「宵祭」など、2日にわたって町は熱気と華やぎに包まれます。
●屋台曳き揃え(やたいひきそろえ)
10.jpg)
秋空の下、屋台11台が櫻山八幡宮に勢揃いする「屋台曳き揃え」の光景は、まさに圧巻のひとことです。
9日・10日とも、からくり人形を飾った唯一の屋台「布袋台(ほていたい)」は境内に、その他の屋台は表参道に並びます。屋台の彫刻や後部を飾る大きな見送り幕、細部に至る構造までじっくり鑑賞できる機会とあって、屋台を囲む人々からは感嘆の声が上がります。
●からくり奉納
30.jpg)
八幡宮の境内では、からくり人形を載せた「布袋台」による「からくり奉納」が披露されます。
見どころは、男女の唐子が3本の綾(ブランコ)を体操の大車輪のように回転しながら渡り、最後に布袋様の両肩へ飛び移る場面。唐子たちの巧妙で複雑な動きと、布袋様が軍配を一振りする仕掛けにぜひご注目を。9人の綱方が36本の糸を操る人形たちの生き生きとした動きに、思わず夢中になってしまいます。
●御神幸(ごしんこう)

神輿を中心に進む祭行列のことを、春の高山祭では「御巡幸(ごじゅんこう)」、秋の高山祭では「御神幸(ごしんこう)」と呼びます。
氏子の繁栄を願い、神様が1泊2日の旅をするとされる御神幸では、「カンカコカン」と鉦(かね)と締太鼓を打ちながら行進する闘鶏楽(とうけいらく)、裃(かみしも)を着た警固など、伝統の装束を身にまとった総勢数百人もの人々が町を練り歩きます。雅楽の音色とともに眺めれば、江戸時代にタイムスリップしたかのよう。

●屋台曳き廻し(やたいひきまわし)
18.jpg)
9日午後に行われるのが、春の高山祭にはない「屋台曳き廻し」という特別行事。神楽台と鳳凰台、そしてその年の抽選で選ばれた2台の計4台が、櫻山八幡宮の表参道から祭区域内を巡ります。
精巧な彫刻や漆塗りの装飾が間近で眺められるだけでなく、計算されたしなやかな動きの美しさも堪能できます。祭の躍動感を直に体感できる、秋ならではのハイライトです。
●宵祭(よいまつり)
37.jpg)
春の高山祭の「夜祭」行事は、秋の高山祭では「宵祭」として親しまれています。日が暮れると、約100個もの提灯が灯された屋台が町をゆっくり巡行。昼間の華やかさとは異なる、幽玄な世界へと誘われます。
屋台が順道場にたどり着くと、「高い山」の曳き別れ歌を歌いながら、屋台はそれぞれの屋台蔵へ。揺れる提灯が闇夜に浮かぶ、ノスタルジックな情景です。
45.jpg)
●秋の高山祭「八幡祭」各行事とスケジュール(2025年)

※雨天時は、屋台曳き揃えはそれぞれの屋台蔵や屋台会館でお披露目。からくり奉納、屋台曳き廻し、宵祭は中止
会場:櫻山八幡宮周辺
期間:10月9日~10日
TEL:0577-35-3156(高山市教育委員会文化財課内 高山屋台保存会事務局)
4.祭りの期間以外は「高山祭屋台会館」で本物の屋台を眺める

櫻山八幡宮の境内にある「高山祭屋台会館」では、八角形の大神輿と実際に祭りで使用される屋台を常設展示しています。優美な装飾をじっくり眺めれば、飛騨の匠たちの見事な職人技を感じられるはず。高山祭の歴史や文化にふれ、魅力をより深く味わえるスポットです。
5.飛騨の伝統工芸に抱かれた温泉旅館「界 奥飛騨」
.jpg)
高山祭を心ゆくまで堪能した後は、北アルプスの麓・奥飛騨温泉郷へ足を延ばしてみませんか。祭り会場から車で約45分の山あいにひっそりと佇む「界 奥飛騨」は、飛騨の伝統工芸をモダンに取り入れた、アーティスティックでぬくもりあふれる温泉宿。
山岳温泉で心と体をほぐし、館内に息づく匠の技に触れながら、祭りの余韻をゆったりと味わうひとときをお過ごしください。
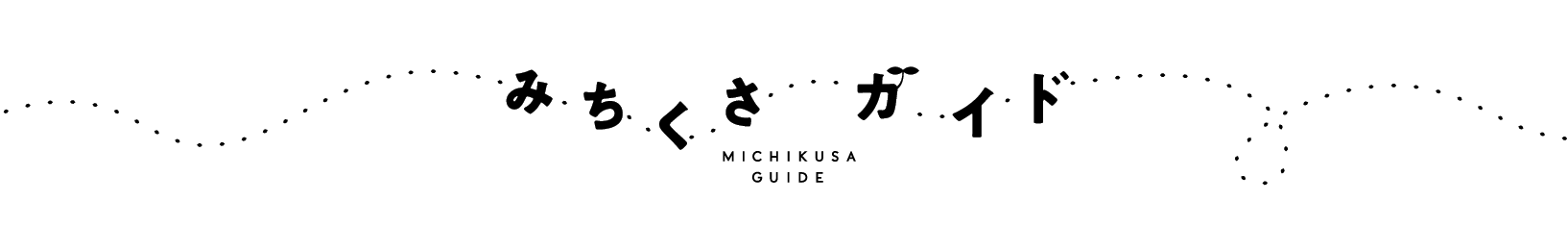




-1-1.jpg)
