日本を愛した文豪・小泉八雲とは? 朝ドラの舞台・松江で文学と歴史を巡る旅
-1-1024x682.jpg)
「耳なし芳一」や「雪女」などを収めた『怪談』の著者・小泉八雲(こいずみ やくも/ラフカディオ・ハーン)。ギリシャ生まれ、アイルランド育ちのハーンが、なぜ日本を訪れ、日本人「小泉八雲」になったのか。八雲と妻・セツをモデルにしたテレビドラマの放送により、その生涯に注目が集まっています。
日本各地に足を運び、移り住んだ八雲。中でも島根県松江市はセツと出会い、日本古来の風物や日本人の精神性に美しさを見出した運命の地でした。
八雲が「神々の国の首都」と呼び、その足跡が色濃く残る松江でゆかりの地を巡る旅はいかがでしょうか。
1. 日本を愛し、日本文化を海外に広めた小泉八雲とは?
ギリシャで誕生。アメリカでの執筆活動を経て、日本へ
.jpg)
小泉八雲、出生名パトリック・ラフカディオ・ハーンは1850年(嘉永3年)にギリシャのレフカダ島で誕生、アイルランドで育ちました。16歳の時に学校での事故で左目を失明。19歳でアメリカに渡り、ジャーナリストとしての道を歩み始めます。
紀行文や翻訳など執筆家として活躍の幅を広げていく中、ニューオーリンズで開かれた万博や英訳の『古事記』などを通じて、日本の文化にひかれていった八雲。1890年(明治23年)、念願の日本に降り立ちました。
松江への赴任。小泉セツとの出会い
.jpg)
来日した八雲は、松江にある島根県尋常中学校と師範学校に英語教師として赴任。身の回りの世話をするために雇われたのが小泉セツでした。セツは八雲の家に住み込みで働くことになり、やがて二人は夫婦として暮らすようになります。
そして英語と日本語という言葉の壁から生まれたのが「ヘルン言葉」でした。ヘルンとは松江の人々が「ヘルンさん」「ヘルン先生」など八雲を呼ぶ際の愛称。日本語の助詞などをはぶき、語順は英語と日本語の折衷という独特な言葉で、二人は絆を深めていきます。
「神々の国の首都」松江での暮らし
.jpg)
松江では英語教師として活躍した八雲。教え子の生徒たちや町の人々との交流を通じて、八百万の神々が息づく地に残る日本古来の風習や文化、精神性に魅力を見出していきます。
そんな松江での一日を綴ったのが、来日後最初の著書『知られぬ日本の面影』の一編「神々の国の首都」。松江の町並みや市井の人々、自然や生き物など城下町の情景を鮮やかに、また伝説なども交えて感受性豊かに描き出しています。
46歳で日本国籍を取得。そして『怪談』誕生へ
.jpg)
約1年3カ月暮らした松江を離れた後は、熊本、神戸、東京と移り住み、帝国大学や早稲田大学で教鞭を執った八雲。46歳の時に帰化が認められて「小泉八雲」と改名。八雲の名は『古事記』に登場する日本最古の和歌の「出雲」にかかる枕詞「八雲立つ」が由来といわれています。
三男一女に恵まれ、1904年(明治37年)に54歳で生涯を終えるまで、様々な作品で日本文化を海外に紹介した八雲。晩年の代表作『怪談』の源は、物語が好きだったセツが八雲に語った日本古来の民話や怪談奇談の数々でした。八雲独自の解釈と表現による「再話」として生み出された怪談作品は、恐怖の中にも畏怖の念や人の情、切なさや懐かしさを宿し、文学作品として深い余韻を残します。
「耳なし芳一」に「雪女」、「ろくろ首」、「むじな」。
八雲とセツがともに紡いだ『怪談』は、誰もが知る不朽の名作として今も読み継がれています。
2. 松江で訪れたい八雲ゆかりのスポット
小泉八雲記念館
.jpg)
小泉八雲の旧居に隣接し、八雲の曾孫である小泉凡氏が館長を務める記念館。八雲の偏見にとらわれない開かれた精神「オープン・マインド」をコンセプトに、その生涯や事績をグラフィックや映像などで紹介しています。
記念館では机や椅子、衣類、キセルといった遺愛品、直筆原稿や初版本、家族写真などの貴重な品々を収蔵・展示。八雲の作品に興味を持ったなら、ぜひ著書や関連書が並ぶライブラリーへ。八雲が紡ぐ世界に、ゆっくり浸ってみてはいかがでしょうか。
.jpg)
小泉八雲旧居
.jpg)
八雲が松江で暮らしたのは、およそ1年3カ月。その後半の5カ月を過ごしたのが旧松江藩士・根岸家の武家屋敷で、現在は旧居として公開されています。「庭のある武家屋敷に住みたい」と願っていたという八雲。屋敷の三方を囲む庭をこよなく愛し、著書『知られぬ日本の面影』の一編「日本の庭」の中でも樹々や石が造り出す美や、虫などの生き物が潜む庭の魅力が綴られています。旧居では美しい庭をはじめ、いたるところに八雲とセツが暮らしていた当時の面影を感じられます。
3. 怪談・奇談が今も息づく場所へ
松江大橋
.jpg)
松江市内を南北に隔てて流れる大橋川に架かる橋で、1608年(慶長13年)、松江城築城の際に架設。現在の橋は17代目で、水の都・松江のシンボルとして市民に親しまれています。
橋の南詰で目に留まるのが「源助供養碑」。最初の工事が難航したことから人柱にされたのが源助で、中央の橋脚は「源助柱」と呼ばれました。八雲はこの悲しい伝説を『知られぬ日本の面影』に記しています。
また八雲は同書において、橋を渡る人々の下駄の音を音楽的、大舞踏会のようで忘れがたいものと描写しています。
松江城
.jpg)
松江開府の祖・堀尾吉晴が1607~1611年(慶長12~16年)にわたって築城。国内に12城のみという現存天守の一つで、国宝に指定されています。最上階には360度見渡す望楼があり、松江市街や宍道湖を一望できます。
築城にまつわる様々な話が残る松江城。石垣作りがうまくいかず、人柱に選ばれたのが美しく踊りの上手な娘でした。以来、城下で盆踊りがあると城が揺らぐことから、今でも松江城付近では盆踊りは行われないそう。
八雲は著書『知られぬ日本の面影』で、松江城を怪奇なものを集めてできた竜のようだと表現し、この娘の話にも触れています。
(松江観光協会提供).jpg)
普門院
.jpg)
1607~1611年(慶長12~16年)頃、松江城と城下町が築かれた際に創建された天台宗の寺院。境内には心字池を配した風情豊かな庭園が広がっています。
境内に建つ「観月庵」は、不昧(ふまい)の号を持つ大名茶人で松江藩松平家七代藩主・松平治郷(はるさと)が度々茶事を楽しんだという細川三斎流の茶室。観月庵では八雲もお茶の手ほどきを受けたそうです。
かつて普門院の正面にあった「小豆とぎ橋」には、謡曲の杜若(かきつばた)を謡うと災いが振りかかるという言い伝えがあり、八雲の『知られぬ日本の面影』にも怪談として登場します。
.jpg)
城山稲荷神社

1638年(寛永15年)、松江藩松平家初代藩主・松平直政が創建。10年毎に行われる式年神幸「ホーランエンヤ」は日本三大船神事の一つで、約100隻の船による大船行列は圧巻です。
境内に立ち並ぶのは、姿形も様々な石狐たち。八雲も個性豊かな石狐にひかれ、度々足を運んだといいます。
八雲の著書『知られぬ日本の面影』には神社創建にまつわる伝説も。松平直政が松江に入城した折、稲荷真左衛門と名乗る美しい少年が現れ、住まいを建ててくれれば城下を火災から守ると告げて消えたそう。そこで社が建立されたといわれ、今も数多くの石狐が神社を見守ります。

- 城山稲荷神社
-
 島根県松江市殿町477 MAP
島根県松江市殿町477 MAP
 一畑電車松江しんじ湖温泉駅から徒歩約20分
一畑電車松江しんじ湖温泉駅から徒歩約20分
JR松江駅から車で約7分 JR松江駅から「ぐるっと松江レイクラインバス」乗車約10分、「国宝松江城(大手前)」下車徒歩約10分
JR松江駅から「ぐるっと松江レイクラインバス」乗車約10分、「国宝松江城(大手前)」下車徒歩約10分 参拝自由
参拝自由 0852-21-1389
0852-21-1389 無し(市営松江城大手前駐車場他利用)
無し(市営松江城大手前駐車場他利用)
4. 八雲お気に入りの和菓子をお土産に
一力堂 京店本店「ハーンの羊羹」
.jpg)
京都、金沢と並ぶ「日本三大菓子処」として名高い松江。大名茶人として知られる松江藩松平家七代藩主・松平治郷(茶号 不昧)が築いた茶の湯文化が今も息づいています。一力堂は江戸時代の宝暦年間(1751~1764年)に創業し、初代より代々松江藩の御用達を勤めた老舗の菓子処。
甘党だったという八雲が特に好んだのが羊羹で、東京に移住してからも妻のセツが松江から取り寄せていたそう。「ハーンの羊羹」は当時の味を蘇らせるべく、一力堂六代目当主が記した製法帳を基に再現した自慢の逸品です。
5. 「界 玉造」の滞在プログラム「小泉八雲を辿る旅」で八雲の世界観を味わう
日本最古の温泉の一つといわれる玉造温泉に佇む温泉旅館「界 玉造」。全客室に備えられた露天風呂での湯浴みをはじめ、山陰の海の幸や日本酒発祥の地といわれる島根の銘酒、島根の伝統文化や民藝に触れるアクティビティなどが楽しめます。2026年3月20日までは滞在プログラム「小泉八雲を辿る旅」を実施。八雲を深く知り、その世界観に浸ってみてはいかがでしょうか。
人力車で八雲ゆかりの場所を巡る

「人力車ガイドツアー」では、八雲が好んで利用したという人力車で小泉八雲旧居や松江大橋、怪談の舞台となった寺院などゆかりの場所を巡ります。松江を知り尽くしたガイドの案内を聞きながら、八雲が見たであろう風景を追体験できるプライベートツアーです。
「八雲酒セット」を味わいながら怪談を堪能

夜の楽しみは、館内のお茶室で開催される「怪談茶室」。まずは八雲の生涯や『怪談』執筆の背景の解説、続く「雪女」と「耳なし芳一」のオリジナルの映像演出を交えた朗読で、八雲が紡いだ怪談の世界へと誘われます。
名作とあわせて味わえるのが、八雲が晩酌のつまみに親しんだという和菓子「黄身しぐれ」と日本酒の「八雲酒セット」。黄身しぐれは餡に日本酒を用いた界 玉造オリジナルです。日本酒はにごり種など3種類を用意。美酒とともに珠玉の物語を堪能できます。

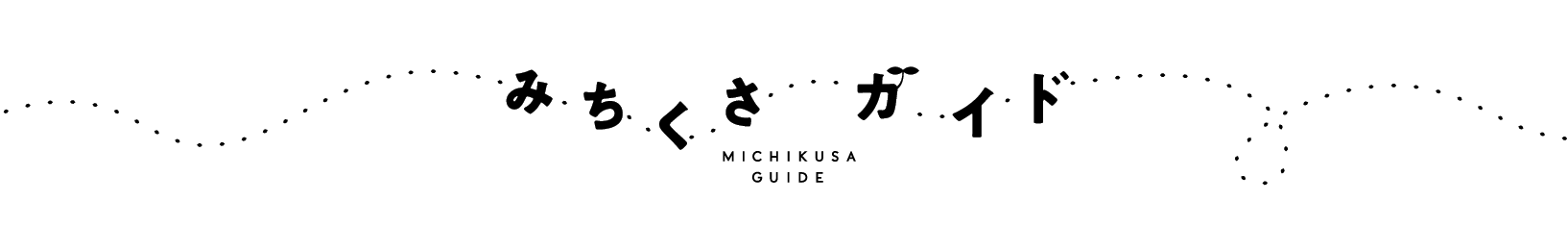

.jpg)
(松江観光協会提供).jpg)
.jpg)





